神話を破壊する――オーウェルの生身の肉体を備えた人間像
小川公代(上智大学教授)
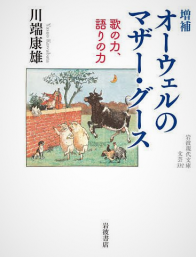
本体 1,520円
A6判 494頁
岩波現代文庫
1.歌の力、および語りの力
「オーウェリアン」(Orwellian)という形容詞が新聞媒体などで 用いられるとき、そこには現実世界があたかもオーウェルが描いたディストピアの世界、つまり希望が語られる余地のない世界に支配されているさまを表すことが多い。たしかに、オーウェルが作家生活を送っていた時期の大半は、スペイン内戦、ファシズム体制下のイタリア、ナチスドイツ、スターリン治下のソ連などの権威主義や全体主義がありふれていた。つまり、『動物農場』にしても、『一九八四年』にしても、全体主義の権力形態を不可避の結論とする物語をオーウェルが意図していたと考えることはできる。とりわけ後者は、人間らしい言葉や「愛」までもが検閲され、愛国心だけが許される殺伐とした世界が描かれている。本書は、そのような受動的な姿勢だけをオーウェル文学に見出すことに抗する読解を提供してくれる。オーウェルの小説が「歌の力、および語りの力」を信頼する「物語作者」によって書かれたことを力強く論じているのである。
具体的な例をあげよう。本書の第一章には、『一九八四年』のなかでプロール階級(労働者階級)の女性が登場する場面が紹介される。それは、全体主義体制の“目”を逃れてジュリアと密会している主人公ウィンストン・スミスが部屋から外を眺める場面であるが、そこに洗濯をする女性を見出している。オーウェルの「ポジティヴな構え」がいかにこの閉じた世界に穴を穿ち、その「穿たれた穴から(中略)一条の光が思いがけず、射しこんでくる」かを本書はこの労働者階級の女性の存在に喩えている。
まったく思いがけず、である。洗濯をするあの愛すべき女性が、抑圧的な歌曲を、彼女が祖先から受けついだ歌う身ぶりの力(フォークロアの力)によって「ほとんど快いしらべ」に変えてしまうときのおもいがけなさと、それはよく似ている。(五八頁)
このように、本書はプロットを推進させる主要部分とは無関係であるように思われる場面にあえて注目することで、異化作用を生じさせている。
改めて『一九八四年』のこの場面を読んでみると、確かに「抑圧的な」ものを「快いしらべ」に変える力が描きこまれていると感じられる。本文には、次のように、ウィンストンはこの「歌」によって、彼の現実世界がいかに生の欲動に対して閉じられているかを気づかされるのである。「これまで、党員が一人で自ら進んで歌っているのを聞いたことがないという事実にふと思い至って、不思議な気がした。それは独り言を口にするのと同じで、いささか正統から外れた行為、危険な奇行であると看做されたのかもしれない」。[1] この場面は、確かに「大きな物語」とは切り離されてはいる。“ビッグ・ブラザー”の存在、ウィンストンが勤務する真理省で改ざんされる「真理」、あるいは三つの超大国が互いに交戦状態にあることが「神話」であるとするなら、「ふつう」の人々の「小さな物語」はその神話を打破する力を有する。本書は、このような「ふつうの人」が「自ら進んで歌」う姿のなかにオーウェルの希望を見いだす姿勢を発見しており、その歌う力を手がかりにしながら、複数の作品を読み解いた野心的研究の成果である。
2.動物の寓話で神話を破壊する
オーウェルは『動物農場』の「ウクライナ語版のための序文」に、ソヴィエト体制の全体主義的プロパガンダが民主主義の国に与える悪影響について書いているが、彼はなぜ西欧の人々にその実情を伝える方法論として〈動物〉の寓話を用いたのだろうか。オーウェル自身はスペインから脱出できたが、仲間の多くは射殺されたり、投獄されたりした。彼にとって、このような人狩りの告発が虚偽であることを突きつけられる経験は、「貴重な実物教育」であった。[2] 彼は、ある出来事に遭遇し、動物にたとえた物語を思いつく。
ある日(当時小さな村に住んでいた)、十歳ぐらいの小さな男の子が、巨大な輓馬を駆って狭い小道を進んでいるところに行き合わせた。馬が向きをかえようとするたびに鞭を当てている。そのときわたしはふとこう思った――このような動物が自分の力を自覚しさえすれば、わたしたちは彼らを思いどおりに操ることなどとうていできないだろう。そして人間が動物を搾取するやりかたは、金持ちがプロレタリアートを搾取するのと似た手口なのではあるまいか。
『動物農場』では、ジョーンズという人間の農場主を追放することで、動物たちが革命をはたすと、彼らのうちで最も知能が高い豚たちが、「人間が搾取するやりかた」を踏襲し、彼ら自身が特権を手にする。権力闘争の末にナポレオンという豚の独裁体制が確立し、人間が支配していたときより、「ある意味ではもっと不自由で悪質な社会になりはてる」のだ(八九頁)。オーウェルは「他国語に簡単に翻訳できるような物語」、つまり動物の寓意で「ソヴィエト神話を暴露すること」にした(「ウクライナ語版のための序文」、二一六)。
この小説の分析に関しては、老いたロバをめぐる論がとりわけ秀逸である。権力者の豚でもなく、過酷な労働によって死に追いやられる馬でもないこのロバのベンジャミンは、豚たちが深夜に改竄を行なっていた事実を知りながらも、「はなづらをふってうなずき、わかっていたようですが、なにも言おうとしませんでした」。このふるまいからも推測できるように、ロバは社会に蔓延する「ふつうの人」のシニシズムを体現している。確かにこの点において、ロバは、政治に対して無関心で諦観を決め込んだ人々の姿を彷彿とさせる。ベンジャミンは「改変・捏造の過程についても十分に記憶している」にもかかわらず、その「知力を政治的に生かして、農場の民主化のために働こう」とは考えなかったからだ(一四六頁)。
しかしながら、本書が注目するのはこのようなロバの“受動性”ではない。ここでもやはり詩に着目している。動物たちの精神歌となる詩については諸説あるが、「お菓子の国」との連想が強いというのが本書の主張である。ここには、「いつも食うことに苦闘しなければならなかった貧しき者たちのユートピア」の要素が揃っているというのだ(一五五頁)。そして、民衆の欲求を表す「豊穣のイメージ」を織り込む歌詞に『動物農場』の動物たちが「熱狂」したのは、この歌の中身が「民衆的ユートピア」を内包していたからとも言える(一五六頁)。オーウェルにとって、フォークロア、つまり過去のおとぎばなしや伝承童謡は、民衆にとって「一緒に考える相手」であり、「思考のヒント」の役割を担っていたのである(一六九頁)。
3.「ふつうの人」という庶民性
本書でオーウェルにとっての民衆、つまり「ふつうの人」という庶民性が論じられるなか、それがプルーストとの対比される例は分かりやすい。『空気をもとめて』の主人公は「現世的な快楽を大いに好む人物」である。「ふつうの人」たるボーリングの強みは、鬱々とする日常のなかに、清々しい気分に満ち足りる瞬間があることである。本書では、ボウリングが歯科医に行って新しい義歯を受け取って、気分ががらりと変わってしまうところを引いている。彼は、「鬱々として現代社会に慨嘆しているばかりではない。こんなふうに立ち直るところがこの主人公の強みなのである」(二一四頁)。彼は、パブに入って、新しい義歯から葉巻の煙が漏れ出るのをみて、「新鮮で、清々して、平和な気分」になる(二一五頁)。
プルーストの『失われた時をもとめて』では過去の想起の糸口になるのが「マドレーヌ菓子」であるとすれば、タイトルもよく似ているオーウェル の『空気をもとめて』では、主人公のジョージ・ボウリングが少年時代の記憶を喚起するのは「カビ臭」さや「馬糞の臭い」によってであり、そこには特権階級が享受していたものの豊さはない(二二七〜八頁)。同作品は、オーウェル自身も奨学生として入学した私立イートン校の「窮屈な服装」などの記憶の断片も列挙されていて、どちらかといえば貧しい下層階級、あるいは「ふつうの人」の具体的な記憶が綴られている。
本書では、映画論が織り交ぜられることによって、さらに「庶民性」の色彩を帯びている。これまでオーウェルと映画というテーマで論じられた先行研究がほとんどないなか、本書はオーウェル研究における映画の重要性に着目している。チャーリー・チャップリンの映画『独裁者』の評を書いたオーウェルがクライマックスの場面に注目しているのだが、重要なのは、映画のなかでチャーリーが彼に期待されたファシストの演説をおこなう代わりに、「民主主義と寛容と人間の品位(コモン・ディーセンシー)を擁護する力強い戦闘的な演説をおこなうことである。本書は、チャップリンの独特な才能について以下のように言及する。
それは庶民というもののいわば凝縮したかたちのために――少なくとも西洋においては、ふつうの人の心に存在する品位(ディーセンシー)への抜きがたい信念のために――戦う力である。(三三五頁)
オーウェルが綴った評からも分かるのは、彼の目線は常に「庶民」のレヴェルであり、決して支配層のそれではないということだ。
このような事例から、オーウェルは具体的な人物による具体的な行為に政治性を発見しているように思われる。この点について本書では明晰な議論を展開している。オーウェルは、そもそも当時の知識人たちの抽象語偏重の言語使用にみられる硬直性を打破しようと考えていた。彼が、「ブリンプ」という具体的な固有名詞を、同時代イギリスの支配階級を指すかのように用いている。「ブリンプ」とすることによって、「支配者」や「保守反動」といった抽象的な語を避けることができるのである。(四一四頁)。「抽象語」ではなく「生身の肉体を備えた(とイメージされる)具体的な人物像」、つまり一個の独立した人格として見る余地を残すことになる(四一五頁)。本書を読んだ後にオーウェル作品を再読すると、フォークロアの力によって生命を吹き込まれた人間の存在が強く感じられる。この「歌う力」のなかに、評者はオーウェルが描く「ふつうの人」の可能性を見た。本書が「絶望を語ったペシミスティックな書物」としてオーウェル文学を読むことに断固として異議を申し立てるのは、伝承童謡で「みずから遊ぶ物語作者」(五七頁)としての彼の手腕を信じるからであり、評者もその意見に全く賛同するところである。
[1] ジョージ・オーウェル『一九八四年』高橋和久訳(早川書房、二○○九年)二一九頁。
[2] ジョージ・オーウェル「ウクライナ語のための序文」、『動物農場 おとぎばなし』川端康雄訳(岩波文庫、二○○九年)、二一二頁。
[3] ジョージ・オーウェル「ウクライナ語のための序文」、二一六頁。
